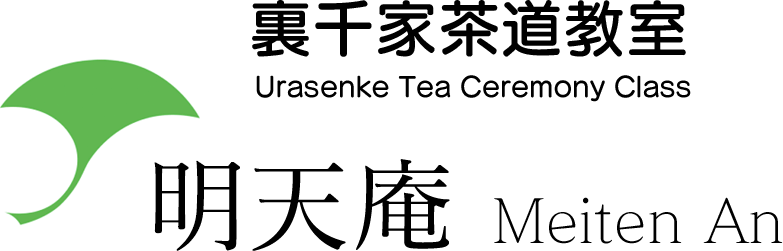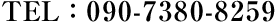茶道への変遷
茶道は抹茶によって執り行われますが、これは茶葉自体においても長い変遷の後に出来上がった作法というわけです。茶葉そのものの扱いも時代と共に変わっており、抹茶をお湯で点てるという飲み方は、日本に茶を紹介してくれた中国では長く忘れ去られた古(いにしえ)の作法でした。近年、裏千家の積極的な日本茶道の啓蒙により、中国においても逆輸入の形で、日本式茶道に関心が集まるようになってきています。
それでは、茶の歴史について概観してみたいと思います。中国において茶について本格的に書かれた書物としては、唐の陸羽(733-804年)の「茶経」です。これには、茶ノ木の育て方、収穫方法、飲み方、歴史など体系的に書かれていました。804年に空海と最澄は帰朝して茶を持ち帰るものの、残念ながらそれほど広くは根付きませんでした。平安時代に入り遣唐使によってもたらせた茶は、貴族や僧侶の間では限局的に飲まれていましたが、いまのお茶とは全く異なるもので、団茶と呼ばれ、茶葉だけでなく、他のスパイスや蜂蜜などと混ぜ合わせたもので、茶の味や効能そのものを愛飲するというものではありませんでした。
鎌倉時代に2度入宋した栄西は、臨済禅を持ち帰っただけでなく、九州の背振山に茶を植え、また宇治の明恵上人(みょうえしょうにん)にも茶の種を送り、宇治茶の起源となったともいわれます。1214年に源実朝に茶と「喫茶養生記」を上梓し、武士階級に茶が広まるきっかけとなりました。「喫茶養生記」は栄西の晩年の著書と言われますが、この内容から当時の栄西だけでなく、僧侶達の役割が見えてきます。この著書は茶の歴史、栽培から点茶法についてまで説明していますが、何と言っても表記が示すように養生について最も民衆に伝えたかったのではないでしょうか。栄西の生きた平安末期から鎌倉初期には、戦乱が絶えず疫病が絶えなかったと言います。当時の僧侶は、個人の悩みや救いだけでなく、個々の予言から国家安寧の加持祈祷まで行うマルチなタスクフォースを期待されていました。当時でも医療職は別にあったようですが、科学的な知識や情報が少なく、最も博識であった僧侶は人間の健康にも深く関わっていたようです。五味五臓という易経は中医学の思想を基に、茶がいかに健康に重要かを説いています。五臓は肝臓、肺臓、心臓、脾臓、腎臓を指しますが、これに五味はそれぞれ酸味、辛味、苦味、甘味、塩味が対応しますが、苦味以外は食事で摂取できるけれども、苦味だけは茶がないと効率的に食することができないと強調します。五臓の中心である心臓を強くするには苦味を有する茶を飲むことが健康にとって重要だと訴えています。
鎌倉時代末期には、飲んだ茶の銘柄を当てる闘茶(とうちゃ)と呼ばれる博打も盛んに催されるようになりました。これは「建武式目」という武家法で禁じられるほど庶民や武士の間で流行したと言われます。さらに富裕層の間では、中国の茶器「唐物」がもてはやされ、大金で蒐集し、盛大な茶会も流行しました(唐物数寄)。この流行は応仁・文明の乱での15世紀後半まで続くことになりましたが、東山文化を築いた室町幕府八代将軍足利義政(1449-1474年)が師事した村田珠光(1442-1502年)は、茶会での博打や飲酒を禁止し、亭主と客との精神交流を重視する茶会のあり方を説いています。義政は1472年に退位し、その隠居所として建てられた同仁斎と呼ばれる四畳半の簡素な小部屋で禁欲的な茶礼と、同朋集(唐物数寄の集団)と中国渡来の美術品の鑑評会を癒合させた書院茶の湯が展開されました。
安土桃山時代に入り、堺の町衆である武野紹鴎とその弟子千利休によってわび茶に至りました。わび茶は、武士階級に広まり、蒲生氏郷、細川三斎、牧村兵部、瀬田掃部、古田織部、柴山監物、高山右近の「利休七哲」と呼ばれる弟子を産み、さらにわび茶から、古田織部、織田有樂、小堀遠州、片桐石州など流派を成す大名も現れるようになりました。これらは武家茶道、大名茶道と、さらに将軍のもとで行われた茶道を柳営茶道などと呼び区別する場合もあります。江戸中期になると、富裕町人階級の台頭により、茶の湯に新たな市場が創出されることとなりました。三千家を中心とする千家系は、大量の門弟をまとめるために家元制度を確立し、七事式という稽古方法も考案されました。これによりさらに庄屋、名主、商人の習い事として日本全国に普及することになりました。同時に、大衆化、遊芸化が進み、「侘び寂び」への理解も変質し、美しい石灯篭を「完璧すぎる」とわざと打ち欠け、破損を接いだ茶碗を珍重するなど、一般の庶民には理解し難い居振る舞いも見受けられるような現象も起こっています。興味深いのは、同じ時代に大徳寺派の臨済宗寺院において「人をもてなす際に現れる心の美しさ」を強調する「和敬清寂」の標語が生み出され、各流派による点前の形態や茶会式の体系化も整備されていきました。
- Nanjōji Temple (Sakai)
- Rikyu Residence Ruins (Sakai)
明治時代にはいると、これまで大切されてきた日本の数多くの伝統芸能、芸術作品、文化が西洋思想の興隆により無価値化していき、茶道を庇護してきた大名、武士階級、富裕層の凋落により茶道も衰退を余儀なくされていきます。裏千家11代玄々斎精中(げんげんさいせいちゅう)宗室は、茶箱点の創始、和巾点の復興を行い、明治5年(1872年)の博覧会で、外国人を迎えるために立礼式を創出しました。この茶道にとって厳しい時代の潮流に対し、裏千家13代の圓能斎鉄中(えんのうさいてっちゅう)宗室は有力財界に理解を得、また女子教育の科目に組み込むなど一定の成果を勝ち取りました。大正時代には、こうした家元が広く庶民層を対象に茶の湯を教え広め、経済基盤を確立してきました。これには維新の功臣、財閥関係者、近世からの豪商など「近代数寄者」が先導した功績も見逃せません。茶道はその後、岡倉覚三(天心)の「茶の本」がアメリカで紹介されるなど、次第に日本固有の文化、芸術、哲学として世界の識者にも認知されるようになり、戦争が終結したあと、14代無限斎碩叟(むげんさいせきそう)宗室は学校教育に働きかけ、各地の寺院・神社にての献茶・供茶を行い、また世界平和を祈願し海外への普及に取り組むなど、積極的な振興に取り組みました。その甲斐あってか、海外の支部を含め流派別では裏千家が最多となっています。
お茶が茶道に至り、今日の有体に成ったことをかなり端折って概観したので、功労や貢献のあった人物の紹介やエピソードを大量に割愛してしまいました。間断なく激動する歴史の荒波の中、様々な賢人たちの努力の結果、現代人はこの日本国の至宝である茶道に接することができていることが読み取っていただけたと思います。ただ、なぜ「お茶」が「茶道」という一つの思想哲学文化にまで昇華されなければならなかったのでしょうか?
茶道は、一つの一人の強い影響で成立したというよりも、星の数ほどある人間の関わりと時間の中で産みだされたということです。表に出ている生き方や美的センス、価値観を分かりやすいように説明しますが、それらはほんの氷山の一角であり、海面下にある思想はとても多国籍であり、さまざまな思想や文化を包摂しているのです。ただそれでもやはり利休居士の時代を超える恣意的なシステムが色濃く反映していると考えられます。利休居士の前の時代も後の時代も現代も、すべての人間が真に平等、対等に接するという機会は殆どないのではないでしょうか。茶道のお点前にも貴人点て(きにんだて)、という作法があります。貴人点ては、そもそもは皇族が参席した場合を想定しており、それ以外はみな平等であるという発想です。とてもモダンというか、今でも職位や社会的地位などでの差別や格差はついて回りますので、現代以上にモダンであるとしか表現の仕様がありません。何をもって平等であると定義するのか。それは、「礼(禮)」によってです。人間が社会生活を行うにあたって、有史以来完全な平等はありませんでしたし、不可能であるばかりでなく有害でしょう。それでも、ヒト一人の生命の価値に上下はありません。生命はみな平等です。利休居士が生きた時代は戦国です。比較的平和な平安時代も江戸時代でもなく、武士などは何人敵を殺したかで立身出世も決定される時代なのです。日々の生活はすべての社会層で、日本という国土すべてがギスギスしていたはずです。四畳半の茶室は、そんな荒廃した時代にあって、権力者も庶民も同じ高さの狭い空間で、一つの茶碗を共有するのです。これは当時の誰にとっても驚天動地、考えられない意識革命だったはずです。しかしながら、何の脈絡もないままに茶室に入っても、そのような平等な人間関係が成立する時間空間を創り出すことはできません。そこで、茶道という「芸道」が必要となったのです。利休居士が育ち修行した堺の南宗寺、京都の大徳寺は禅宗の寺でありながら、儒教をはじめ様々な思想哲学を議論し考えるサロンだったと言われます。儒教の開祖であった孔子は、周の時代の文王、武王、周公旦(しゅうこうたん)などの国家諸制度や教育法に学んだと言います。日本はまだ縄文時代に当たる頃、村里には小学校、諸侯の都には国学、天子の都には大学さえも整備されていたと言います。この各段階の学校では洒掃(さいそう)(水を撒き掃き清めること)、應對(おうたい)(人を呼ぶに応じて問いに答えること。良好な人間関係を構築するための基本的な対応の在り様。)、進退(しんたい)(立ち居振る舞い)の小さな儀礼から始まり、士が学ぶべき、禮(礼節)・樂(音楽)・射(しゃ)(弓術)・御(ぎょ)(馬術)・書(書道)・数(すう)(算法)の六藝を学んでいたと言います。茶道では、洒掃、應對、進退と六藝の禮を中でも稽古の初歩的段階の基本と考えます。禮の本来は、堅苦しいものではなく、家庭、社会における人間関係をより良好にし、正しい秩序を築くための潤滑油です。茶室の中は平等の精神であることには違いありませんが、そこには自ずと違和感のない秩序が生まれていきます。この違和感のない秩序を相互にくみ取るには、お互いの尊敬の念が不可欠です。尊敬の気持ちは態度で表す、それが禮法なのです。ですから六藝の中でも禮が筆頭に来ます。六藝四術の四術は、詩・書・禮・樂の四科目ですが、孔子の弟子三千人が四術を学んでいました。六藝とは技の代表格ですが、六藝を極めた弟子は、その三千人中たった72人だったといいます。実践色の強い六藝を体得することの方が難しかったと言われる所以です。茶道の目的は美しい淀みないお点前の修得ではなく、まず徹底した技(型を含む)=藝を学び、続いて己を中心とした良き人間関係や社会の構築のための行為=道徳倫理を行う。そして高い精神的境地=徳を目指します。そのための教育科目が六藝・六行・六徳の三物(事)です。儒教では徳を得るためにはその前段階としての藝の修得が必要であり、まず六藝の修習から始めると言います。茶道は儒教の教育制度を模して構築されていることが伺えます。このように茶道の稽古に従事する者は、徳を目指すとともに、平等で争いのない人間関係と社会を構築することを目指すことになります。これは、人の生命が尊ばれなかった時代を生き抜き、最後は自刃して果てた利休居士の茶道に秘めた500年の時空を越えた平和希求の理念が生き続け、いまも「ことば」、「一座建立」、「和敬清寂」など作法の中で、利休居士が傍で語りかけているような気がします。
茶道は確かに無数の識者・賢者によって洗練深化してきましたが、お茶が茶道になったのは、利休居士の時代をより良いものに変えたいという悲願がいまの姿を形創っているのだと拡大解釈しています。
日本の統合文化芸術としての顔
「総合文化芸術」ではなく、「統合文化芸術」と表現したのには理由があります。茶道は伝統的重要な文化を数多く包含していますが、すべての文化芸術が含まれているわけではないので、総合ではありません。而して、茶道という確固としたコンセプトの中に、いくつもの大切な芸術が癒合して演出しているおもてなし文化であるという意味で、統合されたひとつの文脈があるのです。それでは、実際にどのような文化芸術が茶道には含まれているのか見ていきたいと思います。
〇陶器、磁器などの焼き物:有名な「一樂、二萩、三唐津」というのは古くからもっとも珍重された濃茶茶碗であり、日本の焼物師がその優劣を競った言葉です。当時有名だったのは、中部―志都呂(しとろ)・美濃(志野・瀬戸黒(せとぐろ)・黄瀬戸(きぜと)・織部)・伊賀、近畿―朝日・赤膚・丹波・膳所・信楽、中国―備前・出雲、九州―高取・上野・薩摩があげられます。また樂茶碗以外で京都において作られた京焼では、仁清、乾山、仁阿弥道八(にんなみどうはち)、永樂家などがありました。
抹茶を入れる茶入にも当時の茶人のさまざまな拘りがありました。茶入は小さな陶器、象牙の蓋をつけ、仕覆(しふく、布製の袋)に入れて用います。茶杓にも象牙が使われることがあります。今ではワシントン保護条約で象牙の輸出入は困難になっていますが、当時でも象牙は舶来品であり、容易に入手できなかったにも関わらず、象牙を用いたのには理由があります。伝説の域を越えないという意見もありますが、毒殺予防であったと言われます。同じ理由で金箔や銀箔も用いられたそうです。これらは毒によって変色して危険を検知するということです。話を戻しますが、茶入とお椀とは同じ陶器でも若干産地が異なります。茶入の代表的な形状は、文琳(ぶんりん)、瓢箪(ひょうたん)、茄子、大海(だいかい)、肩衝(かたつき)などがあります。国焼茶入と呼ばれるものには、備前(岡山)、信楽(しがらき)・膳所(ぜぜ)(滋賀)、丹波(兵庫)、高取(福岡)、薩摩(鹿児島)が当たりますが、国内で焼かれたものを茶入と呼ぶなら、外国で焼かれた茶入もあるの?という疑問が湧くと思いますが、まさにその通りなのです。もとは中国から持たらされた小さな器を茶入に転用して使い始めたのが起源です。概ね福建省福州あたりで、焼造時期は13-14世紀あたりと考えらえています。このような茶入を唐物茶入と呼ぶのですが、この唐物茶入を模倣して瀬戸窯(愛知)で焼かれたものが、他の国焼茶入と区別されて瀬戸茶入と呼ばれています。当時の日本から見た中国というのは、国土も周辺国への影響力、政治力、軍事力、経済力、学術や文化に至るまで圧倒的に進んでおり、憧れと畏怖の大国でした。ですからその中国からの輸入品は、多少の金持ちや政治力では手に入れることは難しい貴重な道具であったことは間違いありません。
このように道具によって生産地も窯元も変わってくる焼き物ですが、500年前に名をはせた生産銘には今もなお多くの方が馴染みをもっていると思います。そうです、これらの生産地や窯元は脈々とその伝統を受け継いでいまも陶器を作り続けているわけです。ただし、茶道具となると、同じ窯元でも値段が倍どころか10倍にも跳ね上がることも稀ではありません。そのようなインセンティブもあっての伝統継承なのだろうと解釈できます。そのお陰で、日常に使用される食器も時々刻々と洗練されたものに進化していると思われます。
磁器も、水入、水指、蓋置、薄茶茶碗、花入れ、香合などいろいろな場面で用いられています。
焼き物の最後になりますが、茶碗もやはり中国産はたいへん高価な貴重品として大事にされました。天目(曜変(ようへん)・油滴・禾目(のぎめ)など)、青磁(砧(きぬた)・天龍寺・七官(しちかん)など)、染付、赤絵、祥瑞(しょずい)があります。とくに曜変天目などはご存じの方も多いかと思いますが、中国では不吉なお椀として一切のこっておらず、日本にのみ現存する世界でも貴重なお茶碗として知られています。いま日中の陶芸家が血眼になって、曜変天目の復刻に鎬を削っていますが、なかなか同じものは出来ていません。さらに朝鮮半島からの高麗茶碗も重用されました。これもいろいろな種類がありますが、刷毛目(はけめ)・井戸・熊川(こもがい)・三島・伊羅保(いらぼ)・斗斗屋(ととや)・御本(ごほん)などが有名でした。
〇釜、鐶、花入れなどの金物:金物の代表格は何といっても「釜」でしょう。釜なくしてお湯は沸きませんので、一連の作業の中でも重要な位置にあります。単にお湯を沸かせるというだけでは満足せず、釜にもその形状や装飾にもずいぶんと熱を入れてきたことが伺えます。主な種類だけでも真形釜(しんなりがま)・阿弥陀堂釜・丸釜・四方釜(よほうかま)、雲龍釜(うんりゅうがま)が挙げられます。有名な生産地として福岡県遠賀郡の芦屋釜、栃木県佐野市の天明釜(てんみょうかま)、京都三条の京釜があります。
鐶付にもこだわっており、松の実や遠山などがあります。
風炉でも鉄製や唐銅製の金物があります。形状もやつれ風炉・鬼面風炉・雲龍風炉・道安風炉・琉球風炉など愉しむことができます。
〇塗り:塗りとして身近に目に入るのは薄茶器の棗ですが、塗り方としては真塗(しんぬり)や溜塗(ためぬり)があり、蒔絵を施すこともあります。この漆塗りの英語訳はJapan(lacquerとも訳されます)であり、漆塗りを見た外国人がその技法の高さと美しさに目を瞠(みは)り、日本を代表する芸術と考えJapanと呼んだことが伺えるでしょう。この塗りという技術によって塗られた器や道具の形状保存だけでなく、食べ物や熱に対しても、漆をぬったものと塗らないものの間には大きな違いがありました。実用性プラスの装飾品としての二つの役割があったのです。これにより、薄茶器のみならず、長板、炉縁(ろぶち)、吸い物椀など様々の場面で塗りの道具は登場することとなりました。
〇竹細工:竹製の茶道具も、お点前の稽古をしているといろいろな場面で出てきます。竹は今以上に各地で容易に手に入る身近な材料であったことは明らかです。そのように誰もが簡単に手に入る「竹」であるからこそ、茶道では結構気軽に茶道具に使用するとともに、大胆に消費する慣習になっているようです。茶杓は作者や銘をもって大切に扱いますが、茶筅などは穂先がささくれれば取り換えますし、蓋置などは青竹の切り取ったばかりの竹が好まれたりします。茶杓は節の無い「真」の点前用、節が切止めにある(元節)「行」そして節が中央にある(中節)の「草」の3つに大別されますが、櫂先の形状、折だめの曲がり、色合いを示す景色などによって雰囲気が大きく変わってきます。さらに「銘」を付けることによって亭主の茶事や茶会への想いを知ることができます。つまり安価で身近な竹細工が、とても大きな役割を果たしていることがわかるのです。柄杓もまた竹製で、月形と差し通しに分けられ、月形は炉用と風炉用の2種類があります。
〇木工用具:棚、長板、炉縁、曲物(まげもの)/木地曲水指、香合、薄茶器など木製の道具は多岐にわたり、やはり作者や亭主のおもてなしの気持ちを表現する大事な役割を果たしています。
〇掛物(かけもの):待合や本席の床の間には、亭主の茶事、茶会開催のテーマが軸として掛けられることが一般的です。最も好まれる掛物は「墨蹟(ぼくせき)」で、もともとは禅宗の高僧の筆跡を指していましたが、現在では僧や茶道の家元によって書かれたものを指します。その中でも禅語が一行に書かれた「一行物」が最も多く用いられています。このほか、「古筆」は飛鳥時代から室町時代にかけて、日本人によって書かれた書があり、和歌・漢詩文・仏典・物語など内容は多岐にわたり、歌集を書写したものが使われます。「絵画」(中国絵画、大和絵、歌仙絵。禅機画(ぜんきが)など)や「画賛」(絵画に賛(詩・歌・文)が添えられたもの)などがあります。墨蹟や古筆など書かれた禅語の意味は、亭主と正客のやり取りにおいて重要になりますが、書自体の巧拙は評価の対象にはならないことになっています。つまり字が下手でも、立派なお坊さんや家元が書いていれば掛物の価値としてはなんら遜色ないということです。それでも古来、日本でも中国での書の美しさは評価の対象となりましたし、「字は体を表す」という言葉のように、字自体が一つの芸術的性格をもっていることは間違いありません。
〇香合と香:香合(こうごう)とは、香を入れる小さな蓋つきの容器を指します。基本的には炭斗にいれて炭手前のときに持ち出します。炉の時季には練香(ねりこう)を陶磁器の香合に、風炉の時季には香木を木地や漆器の香合入れて用いることが習わしとなっています。炭を焚く際、仄かな練香や香木の香りは、また場に新鮮な気持ちや、食事を済ませたあとにほっと一息の安らぎを与えてくれます。良い香りというのは人類にとってもっとも贅沢な営みであることは、昔も今も変わらないおもてなしであり、重要な文化だと言えるでしょう。
茶事に参加する躙口をくぐる際に、客人は靴下を白に交換することが求められます。白い色というのは、当然、汚れが一番目立ちますので、もし洗い立ての清潔なものでなければ一目瞭然です。また今でこそ各家庭に浴室が備えられていますが、このような家屋が日本人の一般的家庭に普及したのはまだ50-60年前の戦後の話であって、それまでは井戸水をかけて身を清める、或いは銭湯にいって身体を洗い流しており、数日に一回が庶民にできる精一杯の清拭でした。水が貴重だったのはなにも日本に限っての話ではなく、かのマリーアントワネットのような王宮で暮らす富裕層でさえ、めったにシャワーや入浴はできず、自分たちの体臭に辟易して発達したのが欧州の香水であったことを鑑みれば、現代人のように毎日シャワーを浴びることが可能な生活環境は、昔の人たちが見たらどれほど羨む贅沢だろうと想像できます。そして利休や江戸時代の生活の中で、人びとの足元といえば裸足であることも珍しくなく、茶事にお呼ばれされる富裕層でさえ下駄や雪駄を裸足もしくは足袋を履いて生活していたわけです。冷暖房もない、道も舗装されていない、交通手段も徒歩しかないとなると、やはり足は汗をかき、埃まみれであることは明らかです。体臭もさることながら、そんな足の匂いを狭い茶室に持ち込まれてしまったら、どんなに貴重で美しい調度品や有難い禅語、そして美味しい料理を振舞われても、きっと心ここにあらず。悪臭で茶事を愉しむどころか、頭痛さえ催してしまうかもしれません。アポクリン線で異臭を伴った素足であったとしても、洗い立ての足袋に包んでしまえば、その臭いはかなりコントロールできたはずです。招待客は、亭主や連客への配慮として、白の足袋に履き替えるのは最低限のマナーだったのかもしれません。足を清めるのは時代劇で、宿場に泊まるシーンでは必ず出てきますし、新約聖書でもマリア(母親ではない)がイエスキリストの足を高価な香油で清めるシーンは有名な逸話です。足の臭いは神の子でもどうしようもなかったのかもしれません。
本論に戻りますが、香木には白檀(びゃくだん)、沈香(じんこう)、伽羅(きゃら)、紫檀(したん)などがあり、伽羅がもっとも高級とされています。大河ドラマでもたびたび登場する蘭奢待(らんじゃたい)は伽羅の代表格でしょう。他方、炉で使用される練香は、各種香料を粉末にして調合する作品であり、製造元によってその香りは違ってきます。
香りはアロマセラピーとして医療の分野でも使用されることもあれば、線香など宗教的行事でも不可欠な構成要素となっています。嗅神経は短時間で疲労して、良い香りも悪臭も馴化されるという特性もあり、この香りにまで配慮するというのは、とても贅沢なおもてなしであり、良い香を焚くことができることは深い知識を有する教養人としての証にもなったことでしょう。
千家十職と言われる、いわゆるご宗家ご用達の道具造りの家柄があります。古くは、十職といわずもっといろんな職人がいたと想像されますが、敢えて10種類の分野に分けて一つの職人の家のみを贔屓にしたわけですから、ある意味とても不公平のような気もしますが、千家は他の職人では認めない、それ程特別の思いと期待を各々の職人一家に寄せていたわけです。
土風炉・焼物師;永楽善五郎
釜師;大西清右衛門
表具師;奥村吉兵衛
竹細工・柄杓師;黒田正玄
指物師;駒澤利斎
袋師;土田友湖
金もの師;中川浄益
塗師;中村宗哲
一閑張細工師;飛来一閑
茶碗師;樂吉左衛門
千家もまた代々続くお家元ですが、お家元という制度は西洋文化圏ではあまり見られませんが、日本ではあらゆる分野に根付いています。その最たるものは天皇家ですが、日本の国体そのものが、実はこのお家元風のシステムに馴染んでいるかもしれません。特にこのような文化芸術というものは、保存して守って発展させるという国全体の決意がなければ、様々な風雪や時代の浮き沈みの中で廃れる可能性があります。日本人は知ってか知らずか、これを他の国よりもかなり意識して庇護しているように感じます。そのおかげで500年前の文化を、それぞれの時代の挑戦を退け、幾分の形式を変化させつつも、いまも愉しむことが出来ている、と言えるのはないでしょうか。
〇懐石料理:懐石料理が文化芸術なのか?と違和感を覚えら得るかもしれませんが、実は懐石料理のみならず、日本食そのものが目的意識をもっていないと守れない可能性が世界的で懸念されているということです。単なる杞憂なのかもしれません。たしかに一方では日本食ブームも指摘されていますので、日本食の一旦を担う懐石料理も発展することはあっても、守る必要があるのかは議論のあるところかもしれません。ただ、日本食とは?と問われて明確に定義づけするのも、異文化交流の中で料理そのものの枠組みが次第に曖昧になって来ているのも事実です。ご承知のように2013年12月にユネスコの世界無形遺産に日本食は登録されました。登録されたのは「和食の文化」と言われます。登録申請の和食の特徴とは以下の4点に集約されます。1.多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、2.栄養バランスに優れた食生活、3.自然の美しさや季節の移ろいの表現、4.正月などの年中行事との密接なかかわり。ここから読み取れるのは、日常と時季の特別な出来事や祝日の両方が和食には求められているということです。
日々の食生活でも、お正月や冠婚葬祭での料理でも、一貫して和食は和食であるということです。そしてこれは文化であると。和食が世界無形文化に登録される前に4つの食文化が登録されていました。「フランスの美食術(2010年)」、「地中海料理(スペイン、ギリシア、イタリア、モロッコ)(2010年)」、「メキシコ伝統料理(2010年)」、「ケシケシの伝統(トルコ2011年)」ですが、これらが登録されたのは、保護しなければ失われてしますかも、という危機感と言います。そう考えると、和食が世界無形遺産に登録されたのは、栄誉でも喜びでもなく、しっかりと日本人が意識していかないと、この食文化が消滅あるいは変容の危険があるということです。懐石料理は、まさに和食の4つの特徴を顕著に表現し、意識する食文化ではないでしょうか。
〇茶室と露地:茶道を学ぶもの、求めるものが最後に実現したくなるのは、自分の茶室ではないでしょうか。それはなぜなのか?茶室を作ったという自己満足、見栄、物欲などもあるかもしれません。利休居士も茶道とは、茶を点て服するだけ、と謳っていますが、それでも茶道の雰囲気、世界観のなかで一椀を手にするのは、やはり格別な時間となります。この茶道の時間と空間を演出するものが、この茶室と露地となります。では露地とはそういった禅的な芸術性のみを鑑賞するための空間なのでしょうか。利休は詠いました。
露地はただ浮世のほかのものになるに 心のちりをなど散らすらん
この場合、露地といっても単なる庭を指しているわけではありません。浮世の外のものとしての茶道の境地を意味しています。浮世にあきたらなくなり、住みにくくなったとき、そういう世界を捨てて、その生活から離れて、侘びの人なり、侘びの営みをするのが茶道の生活であって、その生活体系に一つの筋金を入れることが禅の修行だといいます。しかし、この浮世を厭い、現実世界から離れ世捨て人のように見なされることもありますが、そうではありません。厭世的とか悲観的とかいうことでなく、それらの現実の生活を打ち超えて、現実世界の苦悩を脱却し、新しい積極的生活を創造するのが茶道生活への帰依です。帰依という表現はなにやら宗教的で違和感やアレルギーを覚える方もいるかもしれませんが、茶道生活を意識して生活するという風に表しても良いかもしれません。
侘び寂び
茶道の哲学に目を向けるとき、この「侘び」と「寂び」という耳慣れたフレーズを目にします。しかし、この侘び寂びを正確に説明できる日本人は実は半分もいないのではないでしょうか?この「侘び」「寂び」の思想こそが、日本人の美意識、審美観、そして生き方にも通じるこころの在り様に思います。
「侘び」の説明を辞書から引用すると、①思いわずらうこと。気落ちすること。落胆。万葉集(4)「今は吾は侘びそしにける」②閑居を楽しむこと。また、その所。浄瑠璃、曽我扇八景「侘びのふせ屋の物ずき」③閑寂な風趣。茶道・俳諧などでいう。と書かれています。ここでは③の意味ということになりますが、何ともわかったような煙に巻かれたような気がされる方もおられるでしょう。万葉集に出てくるくらいなので、「侘び」という表現は8世紀からあるということになります。茶道の芽がでる随分前から日本人の間では使われていたことになります。落胆という意味であるなら、現在の用法とは全くことなる意味で使用されていたわけですが、これがどうしていまの用法に変化していったのでしょうか。
一般的には中世(12世紀末、鎌倉幕府成立頃)に近づくころから、本来は厭うべき不十分なあり方に美が見いだされ、不足の美を表現する新しい美意識へと繋がったと言われます。村田珠光(1422-1502年)が「わび茶」の創始者と言われ、室町時代の高価な「唐物」を尊ぶ風潮に対して、より粗末なありふれた道具を用いる方向に変えていったと言われます。珠光はもともと浄土宗の僧侶であり、昔流行した「一休さん」というアニメにもなった有名な臨済宗の一休宗純(1394―1481年)の下で禅の思想に触れ、茶禅一味という茶道と禅の一致を説いたと言われます。この茶の湯のパラダイムシフトを堺の町衆の武野紹鴎(1502-1555年)や千利休(1522-1591年)が深化させていきました。例を挙げると、茶室は「床壁の張付を取り去って土壁とし、木格子を竹の格子とし、障子の腰板も取り去り、床のかまちが真の漆塗りであったのを木目の見える程度の薄塗りにするとか、またはまったく漆を塗らずに白木のままにした」、また茶室の大きさも変わります。「4畳半から3畳半、2畳半に」、6尺の床の間は5尺、4尺へと小さくなり、塗りだった床ガマチも節つきの素木になりました。紹鴎は普段使いの備前焼や信楽焼きを好み、日常雑器から新たな美を見つけて茶の湯に取り込もうとしました。侘びを「正直に慎み深くおごらぬ様」と規定しました。他方、利休は独自の自然で無駄のない茶道具の創出を目指しました。
茶道の侘びの思想を、茶人の山上宗二(1544-1599年)は、「山上宗二記」の中で、「上をそそうに、下を律儀に(表面は粗相であっても内面は丁寧に)」と、「麁相(そそう)」という侘びに近い意味で用いていたことが残っています。また「貧乏茶人」が茶に親しむこと、つまり「侘び数奇(すき)」を評価していたと言われます。他方、現代茶道の実質的設立者である千利休は、この「麁相(そそう)を嫌っていたとも言われ、言葉そのものを嫌っていたのか、思想が違っていたのかは定かではありません。いずれにせよ、わびしさが単に粗末であるというだけではなく、美的に優れたものであることに注目されるようになった時代であることは確かなようです。これは松尾芭蕉(1644~1694年)の俳句や紀行文でより認知されるようになったと言われていますが、実はその前から庶民の美意識の中で萌芽していたとも言われています。侘びが無一物の茶人を言い表し、茶の湯の精神の支柱として醸成されるのは、三代の千宗旦(1578-1658年)からと考えらえています。
このようにして500年以上かけて守られ、深化した思想が、「The Book of Tea」で岡倉覚三(天心)(1863-1963年)によって西洋に紹介され、侘びの精神は日本人のこころとして認識されるようになりました。
つぎに「寂び」について目を向けてみましょう。同様に辞書から意味を引用すると、①古びて趣のあること。閑寂なおもむき。②謡い物・語り物において、枯れて渋みのある声。さびごえ。③太く低い声。④蕉風俳諧の根本理念の一つ。閑寂味の洗練された純芸術化されたもの。句に備わる閑寂な情調。と説明されています。本来は時間の経過によって劣化した様子を意味しています。老いて枯れたものと、豊かで華麗なものという、相反する要素が一つの世界の中で互いに引きあい、作用しあってその世界を活性化する。寂しいという意味での寂は古くは万葉集の中にも歌われています。寂に積極的な美を見出したのは平安時代後期の歌人藤原俊成(114-1204年)と言われ、歌の優劣を競う「歌合せの席で、歌の姿を「さび」と捉え、それを評価しました。その俊成の子が定家で、新古今和歌集の「見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮」が静けさや寂しさを詠った歌として有名で、武野紹鴎によって侘び茶のこころと評されています。
さらに、兼好(1283-1352年)の「徒然草」、室町時代では俳諧や能楽、侘びでも紹介した松尾芭蕉など、文学や舞台芸術でも「寂び」の思想は広く特定の知識人のみならず一般庶民にまで知られ、受け入れられていくようになったようです。特に芭蕉の俳句は、寂をさらに深化させ以後の俳諧に大きな影響を与えた美意識となります。「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、其貫道する物は一(いつ)なり」と説いています。
このように、おそらく多くの日本人が高校を卒業するまでに、これらの「侘び寂び」を深化発展させてきた各方面の芸術家、文化人の名前や作品に触れてきた筈なので、本来であればこれらの説明は不要であり、また知識の再確認に過ぎないでしょう。しかし、実際には「侘び寂び」が誰によって、どのように掘り下げられたかなど、それを専門にする一部の方を除けば、日常や他の勉学の中の一片として意識外に追いやられていたのではないでしょうか。茶道において寂び寂びは、その精神的支柱と説明しましたが、とくに単なる知識としてだけではなく、五感を通じて「侘び寂び」を実践して体現していく反復修練が他の文化活動と大きく異なる点ではないでしょうか。目で視て、耳で聴いて、鼻で嗅いで、手で触り、舌で味わう。人間の知性や知識は感情を伴ったときに、単なる知っている、理解しているから、自分自身の体験、経験として自分の一部へと変わっていくものです。そこに「侘び寂び」の理解の深さが、別の次元へと移っていくと言えます。
茶の湯と禅のかかわり~宗旦の想い
一般に茶禅一味と言われます。本稿で数多くの茶道の特性やその思想の深さ、また芸術性について説明してきました。様々の書籍にも「茶道は禅のみでない」と力説されます。しかし「禅のみでない」と力説するなら、なおのこと茶道の中核思想は禅仏教と理解すべきでしょう。栄西が茶を中国に持ち帰ったから、茶道と禅仏教が結びついたのでしょうか、そんな単純な理由ではありません。もちろん、栄西は「喫茶養生記」をはじめ、茶の効用に関して数多くのことばを残しています。他方、もし茶と禅仏教が一対となることが必然であるなら、中国でもインドでも日本よりも早く茶禅一味が成立していたはずですが、日本のような茶と禅の関係は他の国では見当たりません。日本では村田珠光、一休宗純、武野紹鷗、利休居士など著名な茶人は禅宗の僧侶もしくは人生の多くの時間を禅寺で修行されています。既刊された茶道関連の書籍をみても必ず、茶禅同一味、という言葉で表されるように、茶道と禅はまさに表裏一体としての関係を謳っています。さらなる問いとしては、茶道を修行していて、禅の思想にどれだけ近づけるのか、理解できるのか?という疑問も湧いてきます。
ここでもう一度、仏教、禅、そして茶道との関係を簡潔におさらいしておくことは、茶道の修行を始める、或いは続けるにあたり重要だと考えます。ただし、仏教や禅のように奥の深い思想を簡潔に紹介することは、分かりやすい反面、あるいは分かった気になっただけで誤った理解に繋がる危険性も孕んでいることは言うまでもありません。これを前提として読み進めていただきますようお願いします。
茶禅同一味、これは三代宗旦が遺書として残した言葉です。幼かった宗旦は、祖父利休の自刃を見ていたといいます。その後、罪人として流浪生活を長く過ごし、徳川の世に代わり幕府よりその咎を赦されたあとも、幾度もの要請にもかかわらず政治や歴史の表舞台へは決して出なかったと言います。「我は一生、この藪の中にこそ楽しけれ」と言い、藪の中の自家にいて、「持ち伝えたる器にかえて清貧を楽しめり」(「茶道或問」より)とも言っています。当時の人々は、その姿や生き様から「乞食宗旦」と呼んだと言います。利休居士によって茶道は、一部の為政者の趣味から、多くの権力者や市民の手に渡りました。しかし、利休居士が提唱した侘び寂びの茶道は、必ずしも時の権力者たちに理解されていませんでした。宗旦は、そんな茶道を自分の生涯と茶禅同一味という遺書の中で世に問うたのではないでしょうか。

日本で最初の臨済宗の寺:聖福寺(福岡)